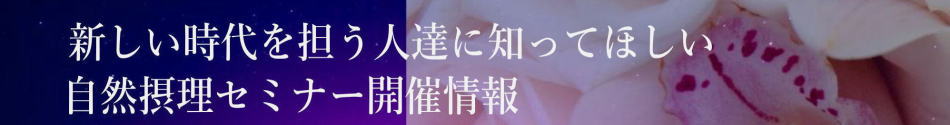B1:基礎理論更新日:2025/08/20
■ 免責事項:必ずお読みください ■
量子生態学は、現在の物理科学による第三者検証が果たされていません。また既存物理科学界は、理解できる研究者がいないとして、関与を拒んでいます。従って掲載理論や関連技術等の関連事項は、今現在提唱者しか把握していません。本サイトや関連資料を基に量子生態学を応用して問題が発生しても、一切の責任を負いませんことをご了承ください。
皆様の研究や技術開発に量子生態学の視点を加えたい場合は、必ずお問合せの上で、アドバイス等をご依頼ください。最高の成果が出せるよう、万全を尽くしてご協力致します。

基礎理論は、私たち人間を始めとする、自然界のあらゆる「もの」の成り立ちに関する、基本システムの理論です。
「もの」は、常に発生しては消えてゆきます。人間も生まれては死にを繰り返し、地球は40億年途切れること無く、「もの」を循環させて存続しています。
水を思い浮かべると、わかりやすいでしょう。
水は3種類の形態を持ち、氷→液体→気体、を行ったり来たりして循環しています。この3つのいずれになるかは、温度条件で決定されます。他のあらゆる「もの」も同じで、自然界では必ず、条件に応じた3種類の形態変化のもとに存在し、例外はありません。
そして、この3種類の変化は、「電子という量子」の動きに依存しています。
目に見える「もの」として形状や性質を作るのも、壊れて形状や性質を変化させたり、やがて「もの」として存在が無くなるのも、水のように氷や液体や気体になるのも、全て電子の動きで決まります。
この一連のシステムを電子移動の視点で説明するのが、基礎理論です。
説明を始める前に、一点だけ、ご承知いただきたいことを記します。
量子生態学の理論には、現在の物理科学と同じ見解と違う見解が混在します。多くの科学研究者や科学を学んだ技術者は、量子生態学の見解をほんの一言を聞いただけで、拒絶や否定の姿勢を示します。
まずは拒絶や否定せずに、違う見解がある可能性を視野に入れて、読み進めてくださるようお願い申し上げます。
お話しの目次です。該当場所をクリックすると、そのパートへ飛べます。
※文章内分子式の表現は、数字や電荷種類など全て元素記号と同じ文字の大きさで、正しい表現ができていませんことをご了承ください。また理論は、実際の研究成果で見いだした内容と共に、自然を扱う中で相互関与を踏まえ自ずと導かれる仮説を踏まえ、総合的に構築していることをご了承ください。
原子は、私たちが生きる地球上の様々な「もの」を作る一番小さな「もの」で、「もの」の原材料のような存在です。
原子1個で「もの」として、特定の性質を発揮します。
原子の種類を元素と言い、自然界に元々ある元素の種類は約90種類程度です。元素の種類には炭素や酸素や鉄などがあり、私たちはたくさんの元素の種類を知っていますが、元素はみなこのように「もの」として存在する、最も小さな単位を持っています。
そしてこれを基に考えると、自然界に存在する「もの」の原材料は、90種類内外の「もの」が全てになります。
現在は人工的に作られた元素の種類もあり、自然界で「もの」の原材料にはなっていない元素も含め、元素種類は118種類とされています。
これらの元素原子を使い、自然界では常に様々な集合を作り、地球上のあらゆる「もの」を作っています。
例として、元素で作られる「もの」の代表として皆さんがよく知る、「水」を見てみましょう。
「水」は、水素原子2個と酸素原子1個が集まり、H2Oという水分子1個になり、この水分子がたくさん集まって、私たちがいつも目で見ている「水」になります。
二酸化炭素は目に見えませんが、炭素原子1個と酸素原子2個が集まり、CO2という二酸化炭素分子1個になります。これをたくさん集めてボンベに詰めた炭酸ガスは、日常生活でよく活用されています。
人体も同じです。人体の96%が、酸素原子・炭素原子・水素原子・窒素原子でできており、タンパク質細胞や体液の水分を、原子の集りとして作っています。
鉄製品も同じで、鉄原子がたくさん集まり、鉄の塊を作っています。
膨大な大きさの地球も、計り知れない宇宙も、小さなアリンコも、全て、どんな「もの」も、何らかの元素原子が集まって成立しています。
このように、自然界のあらゆる「もの」は、様々な元素による原子達の集合体になっています。
1-2・原子は+と-の電気でできている、でも同じ数なので電気は無い
では、原子の原材料は何でしょう?
原子は、「もの」の原材料ですが、原子そのものは、次の3種類のエネルギーで作られています。
陽子=+の電気エネルギー
電子=-の電気エネルギー
中性子=電気エネルギー±0の磁石力
118種類ある元素ですが、それぞれの原子を作る陽子と電子の数は、必ず同じです。
中性子は電気を持たないので、原子全体は電気的に±0になり、原子は電気エネルギーでてきていますが、電気を帯びていません。
1-3・元素には原子番号が付いており、この番号の数の陽子と電子でできている
118種類の元素には、1番から118番までの「原子番号」が付いており、この原子番号の数が、陽子と電子の数になっています。
例えば、原子番号1番は「元素名・水素」です。1番ですから、水素原子は、陽子1個と電子1個でできています。
陽子が2個以上になると、原子には中性子が入り陽子を集めて固定し、原子を作ります。従って、次のような表現になります。
原子番号2番は「元素名・ヘリウム」です。従って2番のヘリウム原子は、陽子2個と電子2個と、中性子でできています。
原子番号3番は「元素名・リチウム」です。リチウム原子は、陽子3個と電子3個と、中性子でできています。
原子番号8番は、「元素名・酸素」です。酸素原子は、陽子8個と電子8個と、中性子でできています。
以後、118番までの元素原子全てが、陽子と電子の個数だけ変えて、同じ表現で説明できます。
1-4・原子は、真ん中に陽子が集まり、周りに電子が配置される
原子の構造は、次のようになっています。
原子は、真ん中に原子核という、陽子と中性子が全部集まる中心があります。
陽子が何十個になっても真ん中に集まり、中性子も真ん中にいて、原子核という中心を作ります。
この原子核の外側には電子軌道という、電車の路線に似たシステムがあり、ここに電子が配置されます。
例えば、「東北本線の湘南ラインには指定席○個ある」、というように、電子には「電子殻(東北本線に該当)という大きな領域に、数種類の電子軌道(湘南ラインに該当)と、それぞれに電子が入る数の指定席が用意されています。
電子殻は1殻~7殻まで7種類あり、電子軌道はs・p・d・fの4種類、それぞれの指定席の数の間には、決まった関係があります。
1殻=s軌道(2席)=合計2席
2殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)=合計8席
3殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)=合計8席
4殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)+d軌道(10席)=合計18席
5殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)+d軌道(10席)=合計18席
6殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)+d軌道(10席)+f軌道(14席)=合計32席
7殻=s軌道(2席)+p軌道(6席)+d軌道(10席)+f軌道(14席)=合計32席
原子番号1番から118番まで、電子が一個ずつ増えて元素の種類ができるので、1殻から7殻の指定席の合計数は、118席になります。
この軌道の持つ指定席には、電子が入る位置と数に関するルールがあり、決められた所に決められた数だけ、決められた順番で、配置されます。
また、電子はペアで存在する傾向があり、それ故に全ての座席が偶数になっています。
ただし原子番号1番~118番まで、必ず順番通りに電子が配置されるわけではありません。空いたままの指定席がある代わりに、違う席ではダブルブッキングが起きており、自然界には番狂わせの現象があります。
電子軌道内の電子配置により、各元素の種類ごとに空席状況が変わります。空席の特徴が、原子の繋がり方を左右し、電子共有の作り方、電子移動の方向性、移動する電子の個数を左右し、各元素原子の個性を作っています。
基礎理論では細かな説明を省きますが、自然界の「もの」を理解するには、電子軌道と電子配置の関係性を掴むことが、とても重要です。
なお、元素種類ごとの電子配置の様子は、量子生態学用電子配位則表と量子生態学用元素周期表で読み取ることが出来ます。
量子生態学用電子配位則表
量子生態学用元素周期表
1-5・陽子と電子は、中性子の磁石力で位置が維持される
原子の形を維持するのが、中性子の役割です。
中性子は電気を持ちませんが、磁石のような性質を持っています。
中性子の磁石力が、真ん中に陽子を集め原子核を作り、電子を原子核の周りの決まった場所に配置して維持しています。
陽子と電子を繋ぎ止める中性子の数は、原子番号が小さいと陽子とほぼ同じ数です。ただし、原子番号が大きくなるに従い、陽子より中性子の数は多くなります。理由は、電子が配置される原子の領域が広がり、原子核に位置する中性子が影響しなければならないエリアが拡大するためです。従って、原子番号が大きくなるにつれ、中性子の磁石力はより多く必要になり中性子の数が増え、陽子の数よりもずっと多くなります。
陽子と中性子の数の合計を、質量数と言います。ですから原子番号とその質量数がわかれば、それぞれの種類が持つ中性子の数は、該当する元素原子の質量数から原子番号を引くことで確認できます。
ただし自然界において中性子の数は、それぞれの元素種類で陽子と電子を繋ぎ止めるために必要な数よりも、多かったり少なかったりする場合があります。これを同位体と呼びます。このうち放射能力を持つ同位体を放射性同位体、そのような能力が無い同位体を安定同位体と呼びます。
放射性同位体は陽子数や電子数と中性子磁力のバランスが悪く、自然界では安定して存在できません。そのため徐々にバランスを取り戻し、安定同位体へと変化します。
バランスを取り戻すため、放射性同位体は陽子や電子や中性子を放出しますが、この放出が放射線として影響し、それぞれに名前が付いています。
余分な陽子を原子外へ放出するα崩壊、余分な電子を原子外へ放出するβ崩壊、中性子の磁力だけ調整するγ崩壊、です。陽子や電子や中性子のいずれかの放出時に、放射線の、α線、β線、γ線、として作用します。
こうして放射線を出しながら放射性同位体が安定同位体へ変化することを、壊変と呼びます。
壊変時間は、原子力工学の研究室で現象を起こし測定する場合と、実際の自然界で壊変する場合とでは、まるで違います。また、放射性元素が存在する環境条件でも変わります。
ところで、水素以外の全ての元素原子は中性子を持ちます。中性子が私たちの生活に直接影響するのは、放射性同位体や放射線類が身近にある場合です。しかしこれらは、日常、殆どありません。従って量子生態学では、通常現象については中性子を考えないで説明を進めます。
量子生態学で中性子の把握が必要なのは、鉱物代謝(他の理論テーマで説明します)などの、特殊な代謝現象を把握する場合です。
では、原子がたくさん集まって成立する「もの」は、どのようにして形を維持してるのでしょう?
膨大な原子達はバラバラにならず、どんな仕組みで繋がって集合を維持しているのでしょう?
それが、電子の共有という仕組みです。
「1・原子とは」で、原子の構造を説明しました。
原子は、真ん中に陽子と中性子が集まる原子核があり、周りに電子が配置されています。
原子が繋がるのは、原子の外側にある電子たちが、複数原子の間に入ることで電子を共有して繋がり、「もの」を作っています。
何個集まっても、どのように集まっても、全て同じです。
「電子が原子と原子の間に位置し、繋がりを担う」仕組みです。
2-2・繋がり方は、部分共有結合、全体共有結合、授受結合の3種類
原子の繋がり方は3種類あり、全て、「電子を共有」して繋がります。
A・部分共有結合
隣り合う原子が、お互いの「特定の電子軌道に同じ電子を配置する=部分共有」して繋がります。イメージは、お父さんの手(片方の原子の電子軌道)とお母さんの手(もう片方の原子の電子軌道)の間に子ども(電子)が入り手を繋ぐと、家族の形(もの)になる様子と同じです。現在の科学用語では、共有結合と呼ばれます。
B・全体共有結合
原子集合の、「全領域内をひとつの場として電子が周回=全体共有」して繋がります。金属に見られる原子結合のため、現在の科学用語では金属結合と呼ばれています。金属塊領域全体を電子が猛烈なスピードで走り回ることで繋がりが切れないようになると同時に、全体の原子が周回する複数の電子を全て共有します。一本の電線の中(原子の集合領域内)を、電気(電子)が全体に流れるイメージです。
C・授受結合
授受結合は、片方の原子の持つ電子が、違う原子の電子軌道に移動して入り、それぞれの原子が+と-の電荷を帯びてしまい、磁石になって繋がる仕組みです。
原則として原子の持つ陽子と電子は同じ数なので電気は±0ですが、片方の原子から電子が1個動き隣の原子に移ると、電子を無くした原子は陽子が1個多くなり+1に帯電します。反対に電子が移った先の原子は電子が1個多くなり-に帯電します。するとそれぞれ、+1の電気、-1の電気に変化(帯電)し、+1と-1になるので磁石のようにくっついて繋がる仕組みです。
このように、電気±0の原子が新たに電気を帯びる状態をイオン化と言います。イオン化した様子を量子生態学では、「帯電した」とか、「荷電した」と表現します。
なお授受結合については、現在の科学用語では、イオン化して繋がるためにイオン結合と言います。
ところで、自然界には、ファンデルワース結合という繋がり方があります。
ファンデルワース結合は、共有結合で生まれた分子の結合角度などの影響で生まれ、結合原理は部分共有結合です。量子生態学で見る電子共有による根本の「もの」の形成には当たらず、基礎理論には入りません。この結合は、現象発生理論という、別のカテゴリで扱います。
量子生態学で見る「もの」の成り立ちは電子の共有だけで捉えるので、「もの」が壊れるとは、「共有する電子が無くなる状態」です。
A・部分共有結合が壊れる仕組み
隣り合う原子が共有する電子が、その位置から無くなると、原子の繋がりは切れて「もの」は壊れます。お父さん(原子)とお母さん(原子)が子どもの手(電子)を離したら、家族の形が壊れる(ものが壊れる)のと同じイメージです。
B・全体共有結合が壊れる仕組み
全体共有結合は、原子の集合領域の最も外側を走る電子が外へ出やすく、外側に動いた電子たちは少しずつ領域外へ出て行きます。こうして全体から電子が減るに伴い、原子の集合領域内の原子間の繋がりは弱まります。多くの電子が無くなると、やがて原子の集合は脆くなり、最後には壊れます。
鉄を思い出すとわかりやすいでしょう。
鉄の塊は、外側にある電子が先に鉄の外に出るので、外側から原子の繋がりが失われ、外側からボロボロになります。
C・授受結合が壊れる仕組み
原子間で電子の授受があり「+1と-1」や「+2や-2」のようにイオン化して繋がった原子の集りの中に、全く違う「新たな+1や-1」、「新たな+2や-2」、「+3や-3」など、今までに無い電荷が関わると、繋がりを維持していた電子が新しい電荷に磁石要素で吸い寄せられます。すると繋がりを担っていた電子は動かされ、結合していた原子は繋がりを失います。
このように、原子を繋ぐどんな結合も、繋がりを担っていた電子が動くと原子は繋がることが出来なくなり、「もの」は壊れます。
自然界に存在する「もの」は、集合する原子が電子を共有することで原子と原子を繋ぎ、成立しています。
電子の共有方法は3つ、原子と原子が電子を部分的に共有する部分共有結合、集合した原子の全領域内で電子を共有する全体共有結合、隣り合う原子間で電子を授受し原子が帯電することでお互いの原子が反極磁石になり繋がる授受結合です。
成立している「もの」が壊れるのは、原子と原子を繋いでいる電子が失われ、原子と原子が離れることで起こります。
部分共有結合は、特定部分の共有電子が無くなると、特定箇所の原子の繋がりが失われます。この例の代表が人体の傷口で、傷口部分は、人体という大きな「もの」の特定部分の結合を担う電子が無くなり発生します。
全体共有結合は、領域内を走り回る共有電子が少しずつ減ると、全体をひとつにまとめる力も少しずつ失われて壊れます。この様子を表現する言葉として、金属疲労があります。金属製品の領域から電子が少しずつ失われ、全体が脆くなる現象です。
授受結合が壊れる様子は、例えば塩味が効いた味付けの料理を、時間をかけて煮込んだり一晩寝かせると薄味になることで、私たちは体験しています。塩化ナトリウムが別の成分と反応して塩素とナトリウムに分解され、塩味感が減ったりまろやかになる現象です。
このように、自然界のあらゆる「もの」の成立と崩壊は、全て電子移動次第です。
「もの」の成立と崩壊は、どんな「もの」も必ず、3つの形態変化を経過して実現されます。
水を思い出しましょう。
水は、氷の時、液体の時、蒸気の時、と3種類の形態があります。
このいずれになるかは、温度で決まることを皆さんは知っています。
他のあらゆる「もの」も、水と同様に、3種類の形態を持っており、同じように温度で左右されます。
一番わかりやすいのは、鉄でしょう。
皆さんがよく知る鉄の姿は、金属塊になっています。水で言えば、「氷」に当たります。
でも、鉄の塊を溶鉱炉に入れると、高熱で少しずつ溶け、カチカチの塊だった鉄もドロドロになります。
これが、「液体」の水と同じ状態です。
そして鉄を、もっともっと高温に晒し加熱し続けると、やがて蒸発してしまいます。
これが、水が「蒸気」になったときと同じ状態です。
いずれも、氷や金属塊のときを「固体」と呼びます。
流れる水やドロドロの鉄は、「液体」です。
蒸発して目に見えなくなったら、「気体」です。
どんな「もの」も、自然界に存在するあらゆる「もの」は、この「固体」「液体」「気体」の3つの形態変化を起こして、成立と崩壊を実現します。
5-2・「生命」の「個体」「液体」「気体」
????
「どんな「もの」も、自然界に存在するあらゆる「もの」は、この「固体」「液体」「気体」の3つの形態変化を起こして、成立と崩壊を実現します。」
この見解に対し、疑問を持った方はいませんか?
はて?
水や鉄の様子はわかりますが、人間や動物や植物などは3つの形態にならないのでは?
そう思った方はいませんか?
人間や動物や植物は固体だけれど、液体とか気体にならないと思う、と。
確かに、人間や動物や植物など生命を持つ「もの」が、水みたいな液体状で存在する姿を、誰も見たことはないでしょう。ですから、そう思うのは当然です。
でも、人体も動物も植物も、3つの形態を持っています。
人間がお母さんのお腹の中から生まれたときは、人体という「もの」で、「固体」に当たります。
動物も昆虫も同じで、生まれたときは、それぞれの動物や昆虫や卵などの、「固体」です。
でも、人間も動物も昆虫も植物も他の生き物も、「もの」としての成立に時間的限界があり、やがて死を迎えます。
日本では殆どの場合、亡くなると火葬されるので理解しにくいかもしれませんが、山の中の動物や昆虫や植物と同じように考えてみましょう。
人間や動物や昆虫類の死骸、成長を終えた植物、などを自然界に放置するとどうなるでしょう?
少しずつ腐敗が進み、やがてどこにあったかわからないほど分解され、姿形が見えなくなります。人や動物の骨や貝殻など、簡単に腐らないものもありますが、数百年数千年の流れの中では同じように姿が無くなります。昔は人体も、土葬という方式で、土の中に遺体を埋める方法で埋葬していました。土葬では、大分昔に埋葬した遺体は骨を残し、姿形は消えてしまいます。
こうした様子を私たちは、「土に戻る」、などと表現しています。
腐敗して「もの」としての存在が目に見えなくなった状態、もとの姿形や痕跡がどこにも無くなった状態を、量子生態学では「気体」になった状態として把握します。
では、「液体」の状態はどこにあるでしょう?
人間も動物も植物も死骸を自然界に放置すると、ドロドロなるタイミングがあります。それぞれの原子構成にもよりドロドロ感は違いますが、液体と同様の現象は、個体の形が崩れ行く過程を意味します。
少しずつ固体の部分が崩れドロドロとの混在部分が増え始め、ところどころ個体が残りながら、最後には「もの」としての形がわからなくなる状態に変わります。
この過程が、「液体」に相当します。
同じように、植物由来の机や椅子、洋服とか鞄とか靴とか、石油製品のポリ容器とかビニール袋とか、有機物も鉱物も薬品などの液体や、なんでもかんでも、日常環境では変化しなくても、何らかの条件を作れば必ず、「固体」「液体」「気体」、と変化する要素を持っています。
5-3・「もの」が形態を変えるとき
どんな「もの」にもこの3つの形態変化があり、「固体」「液体」「気体」のいずれに変わるか要因は、一般的に温度と圧力です。
「1・原子とは」で説明しましたが、元素は118種類が確認されています。
118種類のうち、人工的に作られた元素以外の自然界にもともと存在する元素の種類は、全て通常の気圧もしくは特定気圧時の融点と沸点の温度が確認されています。
融点とは、元素原子が固体から液体に変わるタイミングの温度のことです。
沸点とは、液体になった元素原子が気化して蒸発を始めるタイミングの温度を言います。
水は、1気圧の時、0℃以下で氷という固体になり、0℃~100℃の範囲では液体、100℃を超えると気体、です。
鉄は、常温では固体、1気圧の時におよそ、1536℃を超えると溶け始め2863℃を超えると気化を開始します。
いずれも、固体の条件温度より高温になるに従い液体へ、さらに高温になると気体になります。
ただし全ての元素の種類が、私たちが知る熱環境で、3つの種類に変化するわけではありません。
元素には、私たちが体験し得ない、零下数百℃のレベルでしか姿を変えない種類があります。
例えば酸素は、-218.4℃が融点、-182.96℃が沸点です。
酸素は通常は気体で、固体になるには猛烈な零下の低温です。
私たちが日常生活する温度帯は極寒の地でも-40℃前後ですから、地球上の酸素は、気体でしか存在できません。
酸素と同じように、数十~数百℃の零下温度帯の沸点や融点を持つ元素は、主に質量が軽い1L殻~2L殻の元素と、希ガスやハロゲンと呼ばれる元素種類で、重い元素では水銀しかありません。
しかし、温度がどうであれ、自然界の「もの」を構成する元素原子達は、融点と沸点という条件次第で必ず「固体」「液体」「気体」の状態を作る要素を持っています。
この温度は、元素諸元表からご覧頂けます。エクセルシートにしてあるので、データの並べ替えなどして遊んでみてください。
元素諸元表
また量子生態学では、各元素の諸元を一目で理解できるよう専用の元素周期表を用意しおり、下記より確認頂けます。
量子生態学用元素周期表・無料
量子生態学用元素周期表・B3ポスター・有料
量子生態学用元素周期表摂氏版・B2ポスター・有料
では温度条件による「固体」「液体」「気体」の形態変化は、「もの」の成立と崩壊のメカニズムの視点で何が起こっているのでしょう?
量子生態学では、次のように把握します。
固体は、集合する全ての原子が電子共有で結合され「もの」として成立している状態
液体は、電子共有による原子の結合が成立した部分と、電子共有を無くした原子や分子の散乱が混在する状態
気体は、全ての原子が電子共有を失い、「もの」が崩壊した状態
「もの」を電子共有による原子の集合体と捉えると、それぞれの形態は以上のように説明できます。
つまり「もの」は、「固体」から「液体」を辿る経緯で少しずつ共有電子の消失が進み、ついに共有電子を全て失ない「気体」へ変化し、成立と崩壊を実現しています。
6-2・電子移動を起こす要素
水や鉄で説明したように、温度次第で、「もの」は3種類に変化することは理解できたと思います。ということは、水や鉄は、特定の温度条件に達すると、電子が動き始めることになります。
その温度が、水であれば、「固体の氷」から「液体の水」になるのは温度が0℃以上で、この環境条件になると電子移動が開始される、ということです。
鉄も、「固体の鉄塊」から「液体のドロドロのマグマ状」は、溶鉱炉でおよそ1500℃以上に加熱すれば得られ、鉄原子の結合を担う電子たちはこの温度条件を経験すると、移動を開始します。
では、融点や沸点が猛烈な低温で、日常的な温度帯では電子移動条件が成立しない原子たちが作る生命などの有機物は、どう考えたら良いでしょう。
有機物を形成する元素の種類うち、水素原子・酸素原子・窒素原子は、融点も沸点も前述したように猛烈な低温で、日常的には気体でしか存在できません。同様に有機物形成の中心である炭素原子は、元素種類の中で最も高温でしか液体にも気体にもならず、これも地球の普通の環境ではあり得ない温度条件です。
こうした生物や有機物類に電子移動を起こす要因が、現在の科学用語で言う「酸化現象」です。近代物理科学では、酸化とは電子を奪う作用として定義されています。
6-3・壊す役割を持つ「もの」
酸化を促す要素として皆さんがよく知るのは、活性酸素でしょうか。活性酸素は老化を促すとして、目の敵にされる物質です。量子生態学の視点でも、活性酸素の酸化性は通常の酸素より強く、正常な細胞から積極的に電子を奪い、崩壊を促進して「老化」を早める仕組みを持つと説明できます。
人体の活性酸素ではなく、空気中の酸素も、生活空間で様々な「もの」から電子を奪い、「もの」の形態を変化させています。
酸素はどんなところにも在り、酸素に触れた自然界の「もの」を、崩壊へ導いています。空気中に放置した鉄製品が、酸化されて錆びながらボロボロになる様子は、皆さんもよくご存じの現象です。洋服も様々な生活用品も、空気に触れる場所に置き放置するだけで、「もの」は少しずつ劣化し、長い間に古びた姿に変化します。そして極端な場合は、見た目は姿形はそのままなのに、触ったら一気にボロボロに崩壊するなどの現象を起こす場合もあります。
酸化は「もの」を壊すので怖いと思いがちですが、一方で、電子を奪い積極的に「もの」を壊すことが、とても重要なこともあります。それが私たちの健康を維持するための、食べ物の消化です。
消化は、胃酸が胃の中で食べ物から電子を奪い、「固体」から「液体」に形態変化を促す作用です。胃酸は過剰発生すると問題ですが、食べ物を壊すために電子を奪う役割を担い、「もの」の破壊を有益にしている自然界の現象です。
酸化は電子を「奪う」破壊をイメージし悪い印象しかありませんが、胃酸のように「もの」を破壊に導くことが、役割として大切なことも、私たちは認識する必要があります。
自然界で有機物は、生まれては死にを繰り返していますが、人体の細胞も植物もこの現象により入れ替わりしながら「もの」が循環し、地球は40億年間続いています。つまり電子を奪う作用は、「有機物というものを壊して形態変化を実現」し、「新たな有機物を形成する循環の原因を作る」、とても重要な働きを持つのです。
この重要な働きを担うために、電子を自分へ引き寄せて結合を壊す役割の元素が、もともと自然界に用意されています。それが、ハロゲン系元素と呼ばれる種類で、フッ素、塩素、ホウ素、ヨウ素などです。
私たちがよく知る上記の4種類の元素たちは「もの」を壊す役割が専門で、量子生態学では、壊す機能を持たせる以外に安易に使用してはならない元素種類として定義しています。
現在の日常生活で問題と思われるのは、歯のフッ素塗布と次亜塩素酸による空気清浄機です。
フッ素は電子1個を自分へ引き寄せる性質を持ち、特定の原子と繋がるとものすごく頑丈なものを作ります。この機能性を使い歯に塗布したり、劇薬の容器に使われたりしています。容器はまだしも、歯に塗布すると、体質次第でフッ素の破壊力がダイレクトに作用し、歯がボロボロになる人がいる可能性が潜在します。
また、空気清浄機で次亜塩素酸を使用するタイプは、塩素による殺菌力で室内殺菌には有効ですが、空間放出で少しずつ長い期間人体が吸い込むと、肺の細胞も徐々に壊れる可能性があります。体質次第では、数年、十数年をかけて肺が劣化し、気付いたときには手の施しようが無い病態が発生することも想定されます。
フッ素塗布を過剰に勧める歯科医や、次亜塩素酸応用製品を提供する企業は、こうした危険性を前提にすべきことを、量子生態学では提言します。
6-4・電子移動は「もの」の中に帯電を作る
では具体的に電子移動が起こると、何故、「固体」は「液体」へ、「液体」は「気体」へと変化するのでしょう?
それが、原子の帯電=イオン化、というメカニズムに基づきます。
原子のイオン化は、2-2・「もの」が成り立つ仕組みの授受結合で説明しました。
原子は基本的に陽子と電子の数が同じで±0で存在しますが、授受結合では電子が動くことで、電子の数が減って+に帯電する原子と、電子の数が増えて-に帯電する原子を作り、原子を磁石に変えています。
授受結合以外でも、部分共有結合も全体共有結合も、「もの」の成立から「崩壊」へ向かう過程では必ず電子移動が発生しており、そこには動いた電子の-電荷と、電子が減った原子の+電荷が形成されています。
そして「もの」という特定の範囲内では、この-電荷と+電荷が引き合い反発しながら存在を続け、「もの」全体としては電荷ゼロが維持され続けます。
つまり「固体」から「液体」への変化は、電荷ゼロの原子の世界から、電荷ゼロの原子と荷電した電子や原子が混在する世界への変化です。でも、「もの」としての特定領域内では、電荷ゼロが続きます。
その後すっかり「液体」に変化すると、動いた電子は「もの」の領域から外へ出て行きます。すると、電子と引き合っていた+の荷電原子や分子は引き合う相手が無くなり、単独の荷電原子になり、私たちの目には見えない存在に変化してしまいます。これが、「気体」への変化です。
つまり「固体」から「液体」への変化とは、「もの」の中に電荷を持つ部分を発生させながら、場として電荷ゼロを保つ形態変化です。
そして「気体」から「液体」への変化とは、場の電荷がすっかり+と-に別れ、全てが目に見えないエネルギー状態になったことを意味します。
6-5・「もの」の中の帯電と形態変化の様子
再び、水で見てみましょう。
水は、H2Oという分子の集合体で、氷も同じです。
このとき、氷を構成する原子達は水分子として、全て電荷ゼロで存在しています。
凍っていた氷が溶け始めると、氷を構成する分子の集合体のどこかの部分の、原子と原子を繋ぐ電子が、移動を始めます。
それは、氷の存在環境の温度が1気圧で0℃を超えるタイミングです。この温度帯になると、氷を作る部分共有を担う電子は、それぞれの電子軌道から外れる行動を起こします。
同時に、水分子たちは、H2O以外に、H2Oが2個集りH3O+とHO-という存在を作り始めます。即ちH2Oという電荷ゼロの固体と、電子が動いて生まれるH3O+・HO-の、荷電した水分子が発生します。
でも、総合的な陽子と電子の数は同じで、溶け始めた氷の領域内は電荷ゼロで、「もの」として目に見えています。
やがて氷の成立を支えていた電子たちが移動し、全て所定の電子軌道から外れると、氷を作っていた原子達は、上記の3種類の分子にすっかり変化します。3種類とは、H2O(電荷ゼロの原子の集り)と、H3O+とHO-(+1及び-1になった原子の集り)が散乱する、「液体」の状態になります。
水という特定領域であれば、水滴であっても場としての電荷は±0を維持しており、「液体」という「もの」として目に見えています。
さらに温度が上がると電子移動は活発化し、繋がりを担うあらゆる電子たちが動きます。その結果発生するのが、水分子を構成していた全ての原子が荷電する現象です。もはや電荷ゼロは原子としても場としても存在が無くなり、水という「液体」は私たちの目には見えなくなります。
これが、「気体」という「もの」に形態変化した様子です。
鉄でも説明します。
鉄は、分子では無く単独原子の集として繋がり、常温ではカチカチで、鉄の塊の「固体」を作っています。
このとき鉄は電気を帯びておらず、鉄を構成する原子はFeで電荷±0、電荷はどこにも存在しません。
鉄の塊を溶鉱炉に入れます。
どんどん加熱し、ある温度帯に入ると、鉄を構成していた電子が存在環境の温度を認識し、移動を始めます。
領域内を猛スピードで走り回っていた電子は、外側から少しずつ移動を始めます。
この時の原子は、Feと、離れた電子たち、そしてFe2+やFe3+が混在するようになります。
即ち、Feという電荷ゼロの「粒」と、-電荷を持つ電子や、Fe2+とFe3+のイオン化した原子の混合体、即ち「液体」になっています。
さらに温度が上がると電子移動は活発化し、あらゆる鉄原子の電子たちが動きます。その結果発生するのが、鉄を構成していた全ての原子が帯電した荷電原子になる現象です。つまり全てが、Fe2+もしくは、Fe3+の電荷エネルギーを持ち、移動した電子も-の電荷エネルギーになり、「気化」し、私たちの目に見えない存在に変わります。
人体や動物や植物の形態が変化する過程も、同じです。
人体などの有機物は、分子も複雑で多種類で膨大なので容易に説明できません。しかし、基本原理は同じです。
人体の場合、細胞を作る分子類から電子移動が進み、荷電した分子や原子がどんどん増えながら壊れて行きます。
その過程で、電荷ゼロと荷電原子や分子が混合します。即ち、電荷ゼロの「固体」と荷電分子が混合した「液体」へ代わり、最後には全ての原子が荷電し、全てがエネルギー状態になり、私たちの目には見えなくなります。
電子移動が作るのは、電荷ゼロ → 電荷ゼロと荷電原子の混合 → 全てが荷電した状態、です。
これが、「個体」、「液体」、「気体」の本質です。
6-6・形態変化とは、電荷ゼロの状態とエネルギー状態の交替
固体は、集合する全ての原子が電子共有で結合され「もの」として成立している状態
液体は、電子共有による原子の結合が成立した部分と、電子共有を無くした部分が混在した「もの」として成立する状態
気体は、全ての原子が電子共有を失い、「もの」が崩壊した状態
「個体」から「液体」、「液体」から「気体」へ変化する過程で起こる、電子共有の消失が意味するのは、電子移動で起こる原子や分子の持つ電子数の変化です。電子数変化により、原子や分子は電荷ゼロの存在から電荷を持つエネルギー存在へ変化します。電荷ゼロのときの「もの」は「固体」で電荷ゼロ、これは現在の物理科学界の認識では、「粒」に当たります。そして移動した電子や、電子を失った原子や分子が-や+の荷電すると、エネルギーとして波長を表現する性質の、「波」へと変わります。
現在の物理科学界では、原子が何故、「粒」と「波」の性質を持つのか説明できずにいます。でも、何故持つのかを追求し続けても、誰が何故そうしたのかを解明できる可能性は、とても低いと思います。
それよりも、自然界は確かに3つの形態変化を持っていること、そしてこれは量子が「粒」と「波」を交替している姿だと論ずる量子生態学の見解をまずは認め理論検証を試みる、そんな姿勢を持つべきではないでしょうか。
自然界の全ての「もの」は、「固体」「液体」「気体」への形態変化を通して成立と崩壊を実現し、その実態は、原子が「粒」「粒と波の混合」「波」へ変化することと同義です。
量子生態学では、この粒と波を作るのが、原子を構成する陽子と電子で、これを「量子」として定義しています。
今の物理科学では、原子を作る陽子・電子・中性子や光子、また陽子や中性子を分解して得られるクォークやニュートリノ・ミュオンといった素粒子などを、量子としています。
でも量子生態学では、光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどはの素粒子など、「粒」はもとより存在しない見解です。
従って量子生態学で把握する量子は、陽子・電子・中性子、の3種類を指し、これだけで地球上の様々な自然界メカニズムを把握します。
量子生態学で言う量子は、「陽子」と「電子」と「中性子」で、従って、「原子は陽子・電子・中性子という、3種類の量子の集まり」です。
7-2・量子は、数が変わると、違う「もの」になる
電荷ゼロの原子が集まってできている「もの」は、数が変わっても「もの」は変わりません。
例えば、箱の中に「りんごとみかん1個ずつ」が入っていて、そこへ「りんごとみかん1個ずつ」を誰かが追加したらどうなるでしょう?
答えは?
「りんごとみかん2個ずつ」
正解です。
原子が集まってできている「もの」は、数が変わっても「もの」は変わらず、りんごはりんご・みかんはみかんで、変わりありません。
ところが、量子は違います。
箱の中に、「陽子と電子1個ずつ」の量子が入っています。そこへ誰かが、「陽子と電子1個ずつ」を追加しました。このとき箱の中は、どうなるでしょう?
答えは?
「陽子と電子2個ずつ」
今の物理科学の概念では、正解です。
でも量子生態学の視点では、間違いです。
量子生態学の視点では、次のような回答が必要です。
A・陽子と電子2個ずつ
B・ヘリウム原子1個
C・水素原子2個
ABCの、どれに変わるかは、箱の中の環境に左右されます。
例えば、中性子がどう関与するか、熱や気圧はどのように関与しているか、などです。
ではこの箱の中に、さらに「陽子と電子が1個ずつ入った」らどうなるでしょう?
このとき箱の中は、次の、いずれかになります。
A・陽子と電子3個ずつ
B・リチウム原子1個
B・水素原子3個
C・陽子と電子1個とヘリウム原子1個
D・水素原子1個とヘリウム原子1個
ABCDのどれに変わるかは、中性子や熱や気圧などの環境に左右されます。
もし時間経過と共に環境が少しずつ変わると、さらに様子が変化します。
では、箱の中に「陽子と電子が6個ずつ入っていた」らどうなるでしょう?
このとき箱の中は、次の、いずれかに変わります。
A・陽子と電子6個ずつ
B・炭素原子1個
C・水素原子6個
D・陽子と電子4個とヘリウム原子1個
E・陽子と電子3個ずつと、水素原子1個とヘリウム原子1個
F・陽子と電子2個ずつと、水素原子2個とヘリウム原子1個
G・陽子と電子2個ずつと、ヘリウム原子2個
H・陽子と電子1個ずつと、ヘリウム原子3個
I・陽子と電子2個ずつと、水素原子1個と、リチウム原子1個
J・K・L ・・・とさらにパターンがありますが省略
ABCD・・・・のどれに変わるかは、環境次第ですし、時間経過と共に環境が変わるとさらに変化が起きます。
つまり、量子は、数が変わると、「もの」が変わります。
数が変わった結果、どんな「もの」になるかは、量子が存在する環境によって決定されます。
7-3・電子移動が作る粒と波の世界
量子生態学で見る「もの」の成立と崩壊は、電子移動で発生します。従って、固体という「もの」、液体という「もの」、気体という「もの」も、同じ電子移動で生まれます。
ここで重要になるのは、電子は「量子」であることです。
今説明したように、「量子は数が変わると「もの」が変わる」ことであり、電子が動いて原子や分子が荷電するとは、電子が動いた「もの」は前と違う「もの」に変化したということです。
水素原子で見てみましょう。
水素原子は、陽子と電子それぞれ、1個ずつの組みあわせです。
陽子数と電子数は「+1」と「-1」で±0になり、水素原子は電荷を持ちません。
すなわち、電気を帯びていません。
ここから電子が動き、水素原子から電子だけが無くなるとどうなるでしょう?
水素原子は陽子だけの存在になり、「+1」という電気エネルギーに変化します。
即ち、陽子と電子1個ずつ揃って成立していた水素原子は、水素原子という「もの」で、「粒」という存在でした。
しかし、電子が動いて陽子一個だけになった水素原子は、もう水素原子ではありません。「陽子による+1エネルギー」という量子の存在で、「粒としてのもの」と違う存在の、「エネルギーという波の性質を持つもの」」に変化しています。
元素原子は、電荷ゼロのとき「もの」である「固体」を実現し、このとき元素原子は「粒」として存在します。
元素原子に、電子1個でも増減が起こると途端に原子の量子数は変化し、電荷を持つエネルギーに変わります。このとき原子は「波」として存在します。
こうして「粒」と「波」の性質を持つ原子達は、電子移動を通し、「もの」と「量子」の存在を行ったり来たりして自然界で「もの」の成立と崩壊を担っています。
ここまで見てきた、水や鉄を通し、もう一度、「もの」の成立と崩壊を振り返りましょう。
水も鉄も、「個体」と「液体」のときは全体が電荷ゼロで、量子の数は変化していません。ですから、同じ水や鉄として認識できます。ところが水や鉄が「気体」になってしまったら今までの「もの」としての「場」は無くなり、目に見えなくなります。それは、全てが電荷を持つエネルギーに変わってしまったためです。即ち水も鉄も、みんな量子の存在になった状態です。
「気体」に変わり散乱した量子の数を、私たちは掴めません。今まで水や鉄を作っていた量子は、自然界でその後、数を変えて何になるのか、膨大な組みあわせが想定され、予測は不可能です。
でも自然界では、水がやがて雨になって戻ると同じように、何らかの特定条件に応じ、量子は再び電荷ゼロを獲得し「もの」の成立へと繋がります。
こうして地球自然界のあらゆる存在は、量子で出来ている原子の集合を作り、3種類の形態変化を経て「もの」の「成立と崩壊」を実現し、これを実現するのが、電子移動です。
自然界は、「個体という粒だけのもの」→「液体という粒と波の混合したもの」→「気体という波だけのもの」を経て、粒と波の性質を交替しながら、電子移動を通して「もの」の「成立と崩壊」循環させています。
つまり電子移動の本質は、「もの」の量子数を変えて、自然界に新たな、違う「もの」を作る役割を担っていると言えるでしょう。
懸念するのは、今、人類社会が、量子を操作し始めていることです。人類は、自然界における量子の本質、「量子は数が変わると違うものに変化する」という概念を持たないまま、量子を操作し始めています。
自然界に無い合成分子の創出、原子力技術・人工衛星やロケット開発、多様で膨大な半導体の使用、量子コンピューターの創出、電磁波や放射線装置の多用など、いずれも自然界の本来の量子への影響は、全く想定されていません。
自然界の量子システムの存在を全く認識していない近代科学の知識とこの基に作られる技術や製品は、既に今までに人類が経験したことが無い異常を、地球に対して起こし始めています。
それでも自然界は、人間が量子を操作する行為に順応するだけで、自らには異常という感覚は無いでしょう。
一方、自然界の量子システムが創り続けてきた恩恵を使いたいだけ使ってきた人類社会は、もはや元通りの自然の恵を手にすることは、一切できなくなるでしょう。
8-2・ビッグバンから続く循環世界の本質
量子生態学では、宇宙自然界の最も最初の原点がどのようであったか、わかっていません。一番最初に、何があり、どのように自然界が創造されたのか、皆目見当が付いていません。ただ、地球が宇宙の一員であること、ビッグバンという現象があったことを踏まえると、「もの」の原点となる全ての存在の最初は、エネルギー量子だったであろうと思わざるを得ません。
ビッグバンで+と-と磁力という3種類のエネルギーが発生し、何らかのルールに則り反応を開始し、地球の原点が誕生しました。やがてマグマオーシャンや大気が登場し、温度変化を経て、様々な原子の粒や、有機物の原点粒子が登場し、「もの」の成立が始まりました。
時間経過と共に原子達は3つの形態変化を実現しながら、地球環境と生物相を次々に誕生させて行きます。
しかし自然界の本質はビッグバンにあり、エネルギー量子が漂う空間です。従って電荷ゼロという存在は、多様なエネルギー量子の組みあわせの登場後に、環境が整って以後、誕生したとしか想定できません。
これを基点に自然界の循環を追うと、電荷ゼロのどんな「もの」も、いずれエネルギー量子の存在へ戻らざるを得ないはずでしょう。
地球自然界は、どうあっても、エネルギー量子が作る原子たちの、電荷ゼロの「粒」と電荷を持つエネルギー量子による「波」が交替し続ける循環世界で、本質は「量子」という「エネルギー」的な存在に違いない、というのが量子生態学の見解です。
そしてエネルギー量子の循環は、何度も何度も、永遠に繰り返すことが可能な世界です。
提唱者の世界観
「色即是空・空即是色」
般若心経に見る、この有名な文言が持つ宇宙観は、実に見事と言わざるを得ません。
「色」というたった一言で物質の実在感が伝わり、「空」というたった一言でエネルギー的存在感が表現され、量子生態学の形態変化と循環の世界が、僅か8文字に凝縮されています。
そんな世界に人間が生きていることを仏教は教え、それ故に、全てはいずれ「エネルギー=空」に帰するのだから、「もの=色」に執着すべきでは無い、そう説いています。
提唱者の夫は50年近く、法華経を学び行じています。提唱者自身は経典を熟読することも行ずることもしませんが、門前の小僧で法華経の世界を垣間見て感じるのは、仏陀が提婆達多から学んだ内容は、宇宙自然界を含むあらゆる存在の真理が網羅されていたらしい、ということでした。
それでも、法華経を含む膨大な種類の仏教経典は、多くは仏陀の死後にまとめられ、編纂者の知識が映り、経典ごとに微妙な自然観の誤差がある様相を漠然と感じています。
恐らく、仏教以外の世界宗教も同様ではないでしょうか。
いずれも、数百年、数千年の時を超え、開宗の祖が伝えたかった真理の本意には、少しずつ誤差が生まれていると推測します。
量子生態学による自然摂理を踏まえ専門家が各経典を紐解いたら、もしかしたら、全て共通の真理が描かれていると気付くかと思ったりもします。
遙か昔に仏陀が説いていた自然摂理を、未だ近代科学は見いだせずにいます。
そして、地球が粒と波を介した循環世界であることを人類社会では誰も教えられていないことに、量子生態学提唱者として驚愕し絶望感を覚えることを追記して、基礎理論を終了します。
量子生態学を支援いただくTopetohaプロジェクト

量子生態学理論に基づく生き方のための会員制クラブ

セミナー・イベント情報