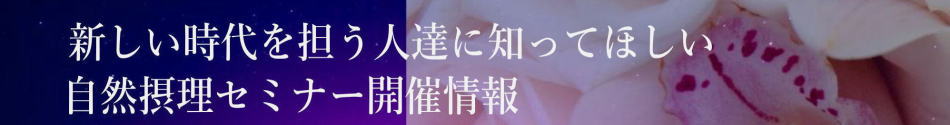下水道業界の罪更新日:2025/09/02

1990年代後半にはリモートセンシングが登場、都市部のヒートアイランド現象が、サーモグラフィで見えるようになりました。また、人工衛星技術で夜間の光環境の撮影も可能になり、電気を使い放題だった日本が日本列島通りの形で光り輝く写真も見かけるようになりました。
河川のコンクリート三面張り護岸が問題視されたり、生態系復活のためにビオトープが重要視されたり、提唱者の専門分野・公園緑地業界でも緑地構成の概念が環境保全重視に移り、緑地業界では、都市熱も光害も懸念の材料になっていました。
日本全体で物を大切にする価値観が生まれ、大手食品業界では生ゴミリサイクル技術に注目が集まり、水質汚染解消技術、水で車を走らせる技術など、エコやリサイクルなどをテーマにした技術開発会社がたくさん登場しました。
この頃、東京都大田区にいた提唱者は、食物や水で病気を治しており、口に入れる成分の質次第で病気になる現実を知り、自給自足を夢見ていました。そればかりでなく、小さな一軒家という閉鎖系空間内で水も電気も調達し、下水は水質浄化して地下に還元したらパーフェクトだと、そんな住宅の実現を目論んでいました。そして、本気で就農を目指し、理想の土地を見つけ、転居した経緯があります。
転居に伴い入手した土地に、閉鎖系空間の資源循環型システムを作り、水道管も電線も下水道管も浄化槽も不要の住宅を建てる夢を持ち続けてきましたが、実現しないまま今に至ります。
この技術の模索の中で出会ったのが、土壌浄化法という下水処置技術でした。
一人は新見正で、もうひとりは名前をすっかり忘れてしまいました。
転居後間もなく、忘れてしまった人が作った土壌浄化施設を見学する機会があり、知った次第です。
提唱者が夫と二人で見学したのは、埼玉県のどこかの町でした。この場所も既に忘却したのですが、とても大きな箱状の施設で小さなエリアごとに排水を集めて浄化し、地下へ返していたと記憶しています。
この施設を数カ所整備して排水処理をしていたこの町でしたが、問題無く稼働していた施設を壊していました。見学当時には、1箇所しか残っておらず、何故壊したのかと聞いたら、下水道網が整備されるため壊されたとのことで、夫共々、仰天したのを覚えています。
戦後の日本は、経済成長はもちろん、国民の近代的な生活の実現を目指していました。提唱者が公園緑地計画に従事したのは1970年代で、国民一人当たりの公園緑地面積を欧米並みにすることを目指し、膨大な設計業務がありました。
同様に近代国家としての公衆衛生確保も喫緊の課題で、戦後間もなく下水道法が作られましたが、その後排水の汚染が問題になり1970年に水質保全が盛り込まれ、大きく法律が改正されました。この経緯の中で、行政の責任による下水道整備が本格化、下水道事業が大規模に開始され、この流れに飲み込まれて施設は壊されたと想定できました。
でも、稼働に問題は無かった埼玉県のとある町のこの土壌浄化施設を、壊す必要はあったのでしょうか?
同じ頃、新見式土壌浄化法と類似施設も、見学に行っていました。
九州熊本県の宿泊施設です。
ここの土壌浄化施設は、土壌の力で汚水を浄化、この過程で発生する窒素などの成分を畑に還元するシステムを作っていました。浄化経路上にブルーベリー畑があり、ブルーベリーが肥料成分を吸い上げる形式だったと記憶しています。そして終末で出てくる水は、汚水とはほど遠い清水で、飲用可能になっていました。
名称は「そよ風パーク」、googleマップで見ると、今も施設は健在なようです。
採用する市町村は現在26自治体、正規の下水処理技術として、導入自治体には政府から補助金が出ることもあるようです。
これらの市町村は、「全国市町村土壌浄化法連絡協議会」という組織を作り相互交流を図っており、そのホームページに次のような文言がありました。
土壌浄化施設設置事例のページより抜粋
「下水道施設計画・設計指針と解説」(日本下水道協会発行)には、未掲載の処理技術ですが、国土交通省の補助事業地として採択されています
農林水産省の補助事業の場合は、建築基準法に準拠して運用されていますが、土壌浄化法は「浄化槽の構造基準・同解説」(日本建築センター発行)には未掲載の処理技術です
土壌浄化法は、市町村単位の大規模な流域を一斉に網羅するのは無理ですが、4000人レベルまで対応可能とされています。また処理水の終末は地下水へ還元されるので、地下水汲み上げで起きている地盤沈下地域では、対策の一つとして有効でしょう。そして何よりも、自然界の土が持つ自然の能力を活かした手法で、高額な処理装置や機械なども不要で、複雑なガス発生などの危険性やメンテナンス種類も少なく、設置費・維持費共に、下水道網整備より、ずっと安全で安価と思います。
つまり、これまでの下水道業界のように派手な利益は出ない、そんなシステムです。
安全且つ税金を節約できる技術なのに、政府が推奨したり規定する技術案件関連書に掲載されないのは、個人的には謎です。
掲載されていたら、情報を得て土壌浄化を導入する自治体や事業者や住宅は、もっとたくさんあったろうと思います。さすれば建設費用は下がり、地方財政はもっと豊かであったかもしれません。
そして土壌浄化施設も下水道網ともども周知されていたら、そもそも埼玉県八潮市道路陥没事故が、起きなかった可能性もゼロではないのです。
思惑や憶測で下水道業界を悪者にするな、そう言いたいかもしれません。でも、技術図書に土壌浄化法の技術を掲載しなかったことがその可能性を秘めているので、何故、何十年も掲載せずにいるのか、その理由を知りたいものです。納得できる理由があれば記載しますので、教えてください。
自然界は、原因と結果しかありません。原因を作ったから今の結果が生まれています。
市町村や政府は、同じ施設形式で再整備を目指すのでしょうか?
提唱者の意見は、今後は自然摂理に沿ったシステムへ、順次入れ替える工夫は、絶対に必要ということです。
今後も未来も、同じシステムのインフラ網を作らなければならないという規則も法律もありませんから、新たなシステムの検討と導入を進めるべきでしょう。
日本では、自然摂理に沿うたくさんの良い技術が、たくさん埋もれているのでは、と推測します。
たとえ良い技術でも、現代社会は利益生産性こそ全てのような概念があります。昔からの智慧で開発された優秀なシステムでも、建設コストが安く儲からない、持続課金できないので儲からない、雇用を増やせないので地方経済に不利、等々の理由で排除され、隠され続けたのかもしれません。
でもそうした思惑は、自然摂理に対しては有効ではありません。
自然摂理に対して有効なのは、自然界のメカニズムに沿うか沿わないか、それだけです。
自然摂理による価値観は、人間社会の価値観とは全く別のところにあります。
もう、いい加減にしたらどうですか?、今のような自然摂理に反する社会システムを作り続けたら、このような事故や災害がまだまだ発生しますよと、自然界がそれとなく警告しているように思います。
自然界と接し続けてきた提唱者には、この自然界の声が埼玉県八潮市道路陥没事故から聞こえてくるようで、責任の一端は下水道業界にも政府の下水道政策にもある、そんな思いでいっぱいです。
これ以上、高額で複雑なインフラ整備の考え方は、もはや破棄すべきと思います。覚悟して、自然摂理に叶うインフラ整備の方向を検討し直すべきでしょう。
八潮市の下水道施設は、莫大な面積の上流域を担っています。この流域を再度検証し直し、小さく分けながら土壌浄化が実現できる可能性を探り、再整備することを検討すべきと提唱者は思います。
例えば、集合住宅やオフィスビルでも可能ですし、小さな分譲地単位でも可能です。
集合住宅やオフィスビルでは、公的規制を作り循環性の土地利用計画を義務化することも、考える必要があるかもしれません。
例えばですが、持続可能性と資源循環を前提に、用意すべき用地面積を、建築面積の最低でも5倍(6倍でも7倍でも)の広さで確保します。
計画地を、A・B・C・D・Eのようにエリア分けし、最初にA地区に建築物を建てます。残る4つのエリアは、住民の皆さんが楽しむアクティビティ緑地、食のメカニズムを誰もが身近に学び活かす生産緑地、そして里山形成エリアを複数箇所確保します。
建築完成から数十年を経てAエリアの建物が老朽化したら、他のエリアへ建て替えます。里山部分は、最低でも100年維持を目指し、最も長期間育成した里山の樹木を伐採し、内装材や家具へ活用します。そして新しく建物が完成したら、もとの土地を、里山やアクティビティ緑地など、無くなったエリア地へ交替します。
もちろんインフラ網は、敷地内だけの整備に徹し自然の力を活かしたシステムでコストを削減し、例えば100年ごとに交代すれば老朽化対策も叶います。
こんな都市計画なら、人口変動への対応も容易ですし、数百年単位のローテーションで自然環境の循環も維持できます。しかも固定した一定地域内のローテションですから、土地取得費用に振り回されず、施設整備中心のコスト検討ですから、長期間を見据えた計画性のある都市計画や街造りが可能になるでしょう。
そんなの現実的では無い、埼玉県も東京都も他の都心部も密集地で、こんなの実施するの不可能だ、などと思うかも知れません。
でも、膨大な費用の下水道の再整備と維持費と比較したら、どうでしょう?
その費用を踏まえれば、工夫の余地はあると思います。
覚悟を決めて、自然摂理に沿う知恵を、みんなで出し合い、やればできると思います。
それが、良い原因を作ることになり、未来の良い結果に繋がります。
世界に先駆けた自然摂理準拠企業のための、量子生態学提唱者によるESG戦略コンサルティング
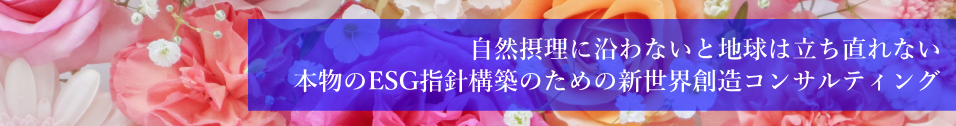
量子生態学、伝言プロジェクト

量子生態学理論に基づく生き方のための会員制クラブ

セミナー・イベント情報